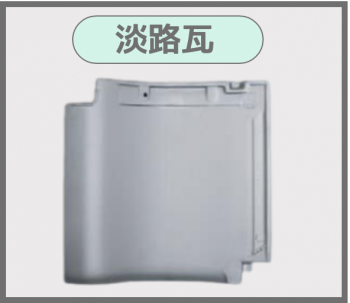三州瓦・石州瓦・淡路瓦が日本三大瓦を誇る理由!

今回のブログは日本瓦とも言われる三州瓦・石州瓦・淡路瓦の
性質や特徴についてそれぞれ調べてみました( ^ω^ )
調べてみると色の付け方や焼成の温度など
それぞれ違った工程があり強みが引き出されて
いることがわかりました。
目次
日本3大瓦
三州瓦(さんしゅうかわら)
愛知県三河地方で生産している粘土が原料でできている粘土瓦です。
生産地の旧国名である三河が名前の由来となり三州瓦となったようです。
自然素材の粘土を原料に窯で焼いて作っていますが
原料となる粘土は長野県・岐阜件・愛知県を流れる矢作川(やはぎがわ)の
下流の粘土を使用しているため、キメが細かく高品質なので
瓦の原料に最適と言われているそうです。
特徴
耐火性
1,100度以上の高温で焼き上げているので耐火性には問題ありません。
このことから建築基準法で不燃物に指定してあり、屋根からの燃え移りを防ぎます。
耐久性
高温で焼いているので焼き締まり、耐久性は非常に高いと言われています。
防水性
塩焼瓦と釉薬瓦は含水率が低く、雨水の浸透を防いでいます。
ただ、いぶし瓦は吸水性があるので防水性が高いものとは言えません。
耐寒性
寒さが原因で起こってしまう『寒割』は水分を瓦が吸収してしまい
瓦の中で凍って、溶けてを繰り返し表面にヒビとなって現れる
現象ですが、そもそも水分をあまり吸収しない塩焼瓦と釉薬瓦は
このような凍害にも強いと言われています。
種類
いぶし瓦
高温で瓦を焼いた後に蒸し焼きにすることで独特の光沢を表現でき
他の瓦では表すことが難しいです。特徴としては吸水性のある瓦なので
吸収した水分は瓦の温度調整をしています。
塩焼瓦
別名、赤瓦とも呼ばれます。瓦を焼くときに塩を投入して焼いていきます
塩が化学反応を起こすことで赤褐色のガラス状の皮膜になります。
塩を数回にわけて焼いていくことで瓦は硬くて強度が増し丈夫になります。
また含水率が低いので寒い箇所に適しています。
塩焼瓦は三州の粘土でなければ美しい小豆色が出せません。
釉薬瓦
表面に釉薬が塗ってあり、ガラスのような層ができコーティングされることで
光沢ができます。釉薬が塗ってあることで水分の浸透も防ぎ強化にもつながります。
三州瓦の取扱があるメーカー
・新東株式会社
∟防災瓦での特許を取得している『セラムシリーズ』が有名で人気な商品です。
石州瓦(せきしゅうかわら)
三州瓦の次に日本で2位の普及率と言われています。
世界遺産としても有名な島根県の石見銀山がある
太田市・江津市・浜田市・益田市の4つの市にまたがる地域で製造されています。
石州とは江戸時代にこの地域が実際に呼ばれていた地名で
それを元に『石州瓦』と名付けられたそうです。
石州瓦は赤色の釉薬瓦が特徴的と言われていて
島根県の山間部では雪がよく降り、日本側は台風の通り道となり
様々な環境の変化がありますが、この環境で作られた石州瓦はとても丈夫と言われています。
石州瓦の赤瓦とは??
分類としては三州瓦にもある釉薬瓦と同じになりますが、石州瓦の赤瓦には
『来待(きまち)』という釉薬が塗られることで赤色を表現しています。
来待釉薬も非常に耐火性が高く、瓦の原料となる粘土は
都野津層(つのづそう)から採れた陶土で、この陶土自体も
耐火性に非常に優れているので来待釉薬と融合されることで
とても強度の高い瓦へと仕上がります。
特徴
防水性
通常の瓦だと小さな気孔があり、そこから水分を吸収してしまいますが
瓦を高温で焼くことによりこの気孔は少なくなると言われています。
1200度以上で一番粘土瓦の中では焼成温度帯が高温なことからも
石州瓦は防水性を発揮し、水分を吸収しにくいことから凍害にも
強いと言われています。
塩害に強い
高温で焼成しているのでとても硬くて丈夫な瓦なので、海水などの塩が
表面から内部へ侵入する可能性は低く、吸収率も低いことから
塩害にも強い瓦と言われています。
変色に強い
石州瓦の独特な来待によるコーティングは変色の原因の
雨などのアルカリ性や酸から守ってくれる働きがあるため
長い間、美観を保つことができます。
石州瓦の取扱があるメーカー
・株式会社シバオ
∟総合防災ウルトラ3s瓦は台風・地震などのでの瓦の飛散防止機能や雨水の侵入を防ぐ防水機能に
とても特化している商品です。
・株式会社丸惣
∟平板瓦のニューセラFというの商品は長期使用対応部材の基準適合商品に認定されていて
防災性能を備え、高い耐久性を持っている商品となります。
淡路瓦(あわじかわら)
淡路瓦は兵庫県の南部にある南あわじ市を中心に製造しています。
瓦自体はいぶし瓦の製造が主で、綺麗な銀色の瓦が印象的なこともあり
いぶし瓦のシェア全国1位にも選ばれています。
淡路瓦の原料となる粘土は『なめ土』という粒子の細かい粘土で
いぶし瓦にはとても適していると言われています。
淡路瓦の窯変(ようへん)瓦とは??
淡路瓦にも、いぶし瓦の他にも釉薬瓦もありますが
釉薬などを使って色を表現する製法ではなく、窯の中の炎で
色をつけていく窯変瓦もとても人気があります。淡路独特の製法で作られていて
自然な窯変の味わいで仕上がりは風合いのある瓦となります。
特徴
耐圧性
寒冷地での積雪やアンテナ工事などによる局地的な荷重にも
十分な強度があるので対応できます。
屋根材に課せられたJIS規格よりもはるかに高い強度を持っています。
劣化に強い
酸やアルカリに対する実験でも高い耐力性を発揮し、
退色・変色もほとんど見られず美観が長く続くことも特徴の一つです。
淡路瓦の取扱があるメーカー
・昭和窯業株式会社
∟現代建築のデザインにも対応できる豊富な役物のラインナップや
淡路瓦の弱点でもあった寒冷地にも対応できる『黒いぶし』という商品もあります。
まとめ
瓦自体は高温で焼き上げて丈夫なものなのでタイルと同様に
50年以上持つとも言われています。
最初の初期費用こそ、スレート屋根や板金屋根に比べると金額が
高いですが耐久性や遮音性は他の屋根材と比べとても抜群に性能が高いです。
また、瓦屋根で恐れられるのが自然災害での被害です。
瓦が飛んでいったり、棟が崩れてしまうなど、
災害が起きた際、テレビ放送でよく目にする光景です。
防災瓦や雨水の浸透率が低いものなど、瓦自体も施工のルールも
自然災害の多いこの時代に合わせて見直しがどんどんされいるようです。
上記では日本3大瓦をご紹介しましたが、瓦のメーカーはまだまだ
数えきれないほどあります!
それぞれに特化した良さもあり進化し続けている日本文化に感動しました( ^ω^ )